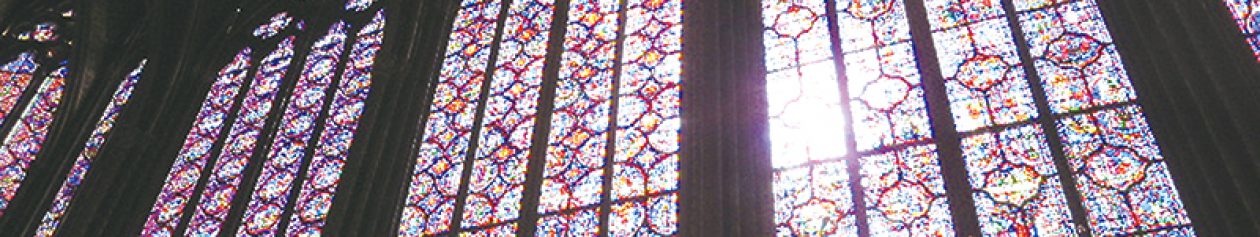最近、イノシシが田畑に出没し、農作物を食い荒らす被害がニュースで話題になっています。農林水産庁の調査によると、令和元年の被害額は約46億円(対前年2%減)にも及ぶそうです。一方で、猪は多産であることから「子孫繁栄の象徴」とされています。また、猪の赤ちゃんは「うり坊」と呼ばれ、その姿を模した「亥の子餅」は平安時代から親しまれています。この亥の子餅は源氏物語にも登場する由緒あるお菓子で、茶道の炉開きにも使われるお菓子です。
ところで、陰暦10月初めての亥の日を祝して食べる丸餅(関東ではのし餅)があります。白・赤・黒の3色の小さな餅に、しのぶなどの添え花をして檀紙や奉書で包み、紅白の水引を1本又は2本かけたものです。宮中の行事菓子「お亥猪包み」と言われるものですが、元来は食べるものではなくお守りのようなものだったとようです。それがいつしか民間に伝わり、亥の日に餅をついて神仏に供えると共に、この餅を食べると無病息災が叶うという風習として伝承されてきました。亥は猪にも通じるため、猪の〝多産”にあやかって子孫繁栄を願って食す意味もあるようです。
旧暦10月は日本全国の神様が出雲に集う「神無月」にあたりますが、出雲に赴かない神様「留守神」で知られるえびす(夷、戎、胡、蛭子、恵比須、恵比寿、恵美須)神を祀り、1年の無事を感謝し、商売繁盛を祈願する「えびす講」が行われる月でもあります。
この「えびす講」は、関東では「二十日恵比寿」とも呼ばれ、毎年1月20日と10月20日に催されます。東京、中央区日本橋の寳田恵比寿神社とその周辺の椙森神社一帯では、江戸時代中頃から続いている「べったら市」が有名です。ちなみに、このべったら市、昨年は10月19日、20日に催されました。この日には露店が数百軒並び、たくさんのべったら漬が店頭並びます。「べったら」の名前の由来は、表面がべとべとしていることからと言われていますが、第15代将軍の徳川慶喜も好んで召し上がったようです。残念ながら、今年はコロナ禍で開催が中止となりました(関西では十日えびすとして1月10日に行われることが一般的だそうです)。
べったら漬けは、塩漬けした大根を米麹と砂糖に漬け、発酵させた食品なので、大根と米麹の栄養を余すところなく摂取することができる美容と健康に良い食べ物。ただし、カロリーも糖分も高いので、食べる量にはご注意を。
うさぎ うさぎ なに見て はねる 十五夜 お月さま 見て はねる ※童謡「うさぎ」より
満月を見ると、つい口ずさんでしまう童謡ですが、この歌詞に出てくる「十五夜」は、旧暦の秋(7月~9月)の真ん中にあたる8月15日の満月をさし、「中秋の名月」と呼ばれています。なお、2021年の十五夜は9月21日になります。
一方、十三夜は旧暦の9月13日の月をさし、中秋の名月に次ぐ美しい月として知られています。2021年の十三夜は10月18日になります。
古来より、十五夜と十三夜の二夜の月見をすることで、縁起がよいと言われています。逆に、どちらか一方の月だけを愛でるのは「片見月」と言われ、縁起が悪いとされています。いままで「片見月」であった方は、この機会に是非「二夜の月見」で良縁祈願をしては如何でしょうか。
寿命には平均寿命と健康寿命があります。健康寿命は、自立して健康に日常生活を送ることができる期間で、残存歯数が健康寿命に関係すると言われています。政府はこの健康寿命の延伸を謳い、厚生省(現厚生労働省)と日本歯科医師会では、1989年(平成元年)より「80歳になっても20本以上自分の歯を保とう」という「8020(ハチマルニイマル)運動」を推進しています。歯を健康に保つためには、毎食後の正しいブラッシングや歯科医での定期的な歯垢除去などのクリーニングが必要です。しかしながら、何かを口に入れる度にその都度ブラッシングをすることは、中々、難しいものです。そこでお勧めしたいのが、口腔内衛生の維持に作用すると考えられている成分・ラクトフェリンです。
ラクトフェリンは、一般的に腸内環境を整える成分として知られていますが、歯周病菌の抑制効果も確認されています。菊医会の高純度ラクトフェリン「心身ともにスッキリ!®」は胃で消化されず、腸まで届いて働くようにした腸溶性ラクトフェリン加工食品です。もちろん、歯周病菌抑制効果も確認されている、販売実績20年の信頼のブランドです。

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の特別措置により、2021年の国民の祝日である「海の日」は7月22日、「スポーツの日」は7月23日に移行しました。ところで7月22日は、「二十四節気」の12番目の節気となる「大暑」として、1年で最も暑い時期になります。この時期はより一層の夏バテ・熱中症対策が必要となりますが、7月28日は「土用の丑の日」。ここはぜひ鰻を食べて、夏バテを克服していきたいものです。出前やお持ち帰りOKなところも増えてきていますから、東京オリ・パラは鰻のパワーを借りながら自宅観戦で盛り上がっていきましょう。
身についた半年間の穢れを祓い、無病息災を祈るための「夏越しの大祓」の後、これからの半年の無事を願い、7月1日以降に神社・仏閣に詣でる「夏詣」という新たな習慣が東京台東区の浅草神社より提唱され、全国に広まっています。また、縁結びのご利益を願いつつ、個性的なデザインの魅力あふれる御朱印集めを趣味とされる方々もいま増えています。今回は、この夏越しの大祓、すなわち夏詣にて期間限定の御朱印をいただける神社の一部(東京都)をご紹介します。
※限定御朱印をいただける期間は、各神社のHPにてご確認ください。
赤坂氷川神社(東京都港区)
http://www.akasakahikawa.or.jp
十二社熊野神社(東京都新宿区)
http://www.12so-kumanojinja.jp/
浅草鷲神社(東京都台東区)
https://otorisama.or.jp/
自宅の紫陽花が色づき始めました。地球温暖化の影響もあるのでしょうか、庭木の植物の開花が例年早まっています。ところで、6のつく日(一説には6月6日とも)にトイレに紫陽花の茎に半紙を巻いて、水引で逆さに吊るすと婦人病の予防になるとの言い伝えがあるようです。紫陽花には霊力があり、魔よけ、厄除けになるようです。兵庫県の若狭野天満神社(あじさい神社)では、“魔除けあじさい守り”で良縁、縁結びを祈願しています。
お見合いや交際中は何かと悩みが多くなりがちです。そんなとき出逢ったメッセージは、貴方に思わぬ気づきを与えてくれるかもしれません。

お御籤を引く感覚で気軽にお楽しみください。
仕事でもプライベートでも、もう少しと思っていたご縁がプツンと途切れてしまう事ってありますよね。そんな時私は “今回はここ迄のご縁だったけど、自分とは違う価値観や考え方を知ることができ視野が広がりました。有難うございました。”って思うようにしています。そして新たな気持ちで次のご縁に向かいます。
さて、コロナ第4波まん延防止で、不要不急の外出がままならない状況ですが、5月といえばこどもの日。五月晴れの空に悠々と泳ぐ鯉のぼり、真鯉に緋鯉に子鯉たちが目に浮かびます。都心ではとんと見られなくなりましたが、東京の2大タワーでは「こどもの日」にちなんだ、こいのぼりイベントが開催中です。東京スカイツリータウンでは5月には1000匹の壮大なこいのぼりが掲揚されます。
こいのぼり(鯉幟)とは、元来、日本の風習で、江戸時代に武家で始まった端午の節句に男児の健やかな成長を願って家庭の庭先に飾る鯉の形に模して作ったのぼりです
【東京スカイツリータウン® こいのぼりフェスティバル2021】
スカイツリーへは、浅草から歩道橋・すみだリバーウォークと東京ミズマチを通っていくのがお勧め。徒歩で約18分(1.4キロ)です。
https://www.tokyo-solamachi.jp/event/1631/
【浅草からスカイツリーまで歩いて約18分】
https://www.tobu.co.jp/odekake/special/asakusatokyoskytreetown/
【東京タワー春の恒例企画!333匹の「鯉のぼり」と「さんまのぼり」】
https://www.tokyotower.co.jp/event/attraction-event/2021-koinobori/
東京タワー周辺は公園や名所・旧跡も多いです。
https://www.tokyotower.co.jp/burari-map/

春といえばさまざまな出会い、はじまりの季節です。
日本人のみならず世界の人々もあこがれる“桜”が過ぎ
いま、そのあでやかな姿が魅力の“牡丹(春牡丹)”の季節が到来です。
牡丹の花言葉は「風格」「富貴」「恥じらい」「人見知り」、
「立てば芍薬、座れば牡丹、歩く姿は百合の花」ということわざがありますが、美しい女性の容姿や立ち居振る舞いを花にたとえたものです。「座れば牡丹」というのは低木で、枝分かれした横向きの枝に花をつけるため、まるで座っているかのように見えるとか。
デートコースの一つとして、上野公園内で開催されている春のぼたん祭りを見て、不忍の池を散策しては如何でしょうか?
お医者様の成婚をお世話し40年!格式ある結婚相談所♥