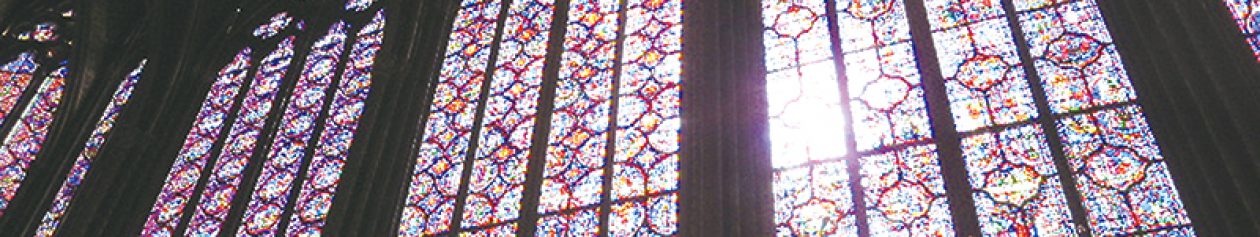夜空を彩る夏の風物詩のひとつ、花火大会が全国各地で始まりました。花火大会はその地域ならではの独自性を持っているため、それぞれの花火大会を巡り、お気に入りを見つけることもまた妙案かもしれません。
そんな花火を日本で鑑賞用として楽しむようになったのは江戸時代以降のこと。打ち上げ花火はその放つ光や色彩、音が、人の視覚や聴覚に大きな影響を与えると言われていますが、一方で、打ち上がってから形になるまでの心に沸き立つ高揚感が、幸せホルモンであるオキシトシンやセロトニン、ドーパミン等の分泌を増やし、人を前向きな気持ちにさせるそうです。
自分磨きにお勧めの展示会情報
スウェーデン国立美術館 素描コレクション展―ルネサンスからバロックまで<2025年7月1日(火) ~ 2025年9月28日(日)>
スウェーデン国立美術館は、世界で最も古い美術館の一つです。中世から現代にいたる美術・工芸品やデザインを幅広く収蔵し、なかでも素描(ドローイング、デッサン)については、質・量ともに世界屈指のコレクションを擁しています。本展は、ルネサンスからバロックまでの名品約80点を同コレクションから選りすぐり、イタリア、フランス、ドイツ、ネーデルラントという地域別の4セクションよりご紹介していきます。
美術の遊びとこころⅨ 花と鳥 <2025年7月1日(火)~9月7日(日)>
日本・東洋の古美術に親しむことを目的として企画している、恒例の美術の遊びとこころシリーズ。第9弾のテーマは「花」と「鳥」です。今回は絵画・茶道具・工芸品に登場する花と鳥をじっくりと観察していただきます。四季折々に咲き誇る美しい花、さまざまな姿で魅せる鳥など、美術の中の花と鳥が織りなす多彩な表現や奥深い美の世界をお楽しみください。
唐絵―中国絵画と日本中世の水墨画<2025年7月19日(土)~8月24日(日)>
遣唐使が停止されたあと、日中間の交流は限られたものとなっていましたが、中世に入ると再び盛んとなり、様々な交易品が日本へともたらされました。それらの中には、中国の院体画や、牧谿ら画僧による水墨画の名品なども含まれていました。「唐絵」と呼ばれたこれらの作品は、とりわけ足利将軍家をはじめとする武家の間で尊ばれ、やがてそれらに倣った和製の唐絵も多数制作されることとなります。根津美術館のコレクションの中には、こうした中国画や日本中世の水墨画といった唐絵の名品が多数含まれます。本展覧会では、それらの中でも特に重要な作品をまとめて紹介いたします。